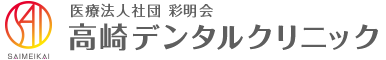硬さより大切な毎日の「よく噛む習慣」

こんにちは。 高崎デンタルクリニックです。
よく噛むことは大切ですが、硬いものを噛むことは本当に良いのでしょうか。
今回は「噛むこと」のメリット・デメリットについてお話しします。
「硬いものを噛むこと」ではなく、「よく噛むこと」が重要
成長期の子どもは、噛みごたえのあるものをよく噛んで、顎の骨や筋肉の成長を促すことが重要です。上顎は小学校低学年から中学年頃に、下顎は思春期に成長します。
やわらかいものばかり食べていると、噛む回数が少なくなってしまいます。そのため、顎の骨が十分に発達せず、歯の生えるスペースが狭くなり、歯並びやかみ合わせに悪影響をおよぼすことがあります。
18歳までの成長期には、顎を健康的に鍛えるためにさまざまな硬さの食材を食べ、噛む回数を増やしましょう。
よく噛むことは良いこと
大人も子どもも、硬いものを強く噛むことよりも、噛む回数を増やすことが重要です。よく噛むことのメリットは以下のとおりです。
- よく噛んで食べるとで、少量でも脳が満足感を得やすくなり、食欲が抑えられて食べすぎを防げる。
- 脳への血流が増加し、脳細胞の働きが活発になるため、反射神経や集中力、記憶力、判断力が向上し、老化や認知症の予防ができる。
- よく噛むと食材の形や硬さを感じることができ、味覚が発達する。
- よく噛むことで唾液の分泌が促され、虫歯予防や消化吸収の促進される。
- 細かく噛み砕くことで、胃腸の負担が和らぐ。
ただし硬いものを噛みすぎると歯や顎に負荷がかかります。
一口につき30回以上を目安に、よく噛んで食べることを心掛けましょう。
よく噛んで唾液の分泌を促す
よく噛んで食べることで、唾液が分泌されます。
唾液には、消化を促進する消化酵素(アミラーゼ)や、のどや食道が傷付かないように食べ物を包み込む働きをするムチンという成分が含まれています。
加えて、食べ物のかすや細菌を洗い流す作用があり、虫歯や歯肉炎の予防にもつながります。唾液の分泌は、消化を助け、お口の健康を守ります。
硬いものを噛みすぎるとよくない?
硬いものばかり食べると歯に大きな負担がかかり、歯が欠けたり、ひびが入ったりすることがあります。歯の根っこがひび割れ(歯根破折)、感染を起こすと抜歯が必要です。
また硬いものを噛みすぎると顎の筋肉を酷使してしまい、頭痛や肩こり、顎関節症などを生じる恐れがあります。
おせんべいや豆菓子、フランスパンなどの硬いものは食べすぎに注意しましょう。
まとめ
よく噛むことは、健康なお口を保つことができたり、脳の働きを活発にさせるなど、さまざまな面で役立ちます。
硬さよりも「噛む回数」を意識し、一口につき30回を目安に食べることで、満腹感や味覚の発達、老化や肥満の予防にもつながります。
日常の食事で、バランスよく噛む習慣を身に付けましょう。
初診WEB予約
お気軽にお問い合わせください。